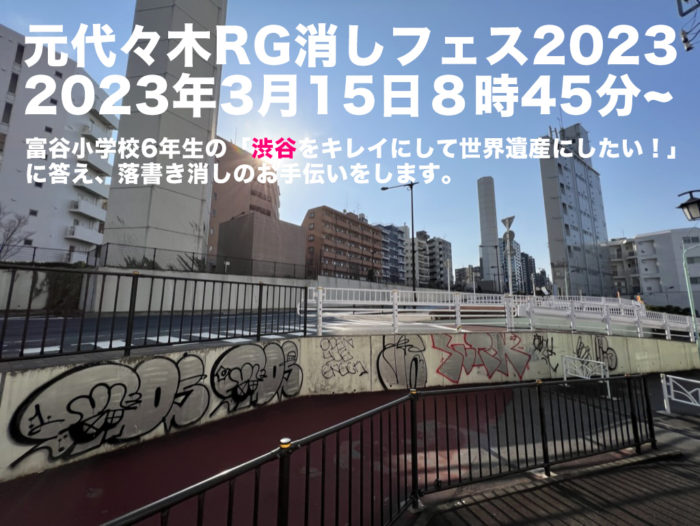今日は2011年3月11日から5,114日
730週4日
14年
168回目の11日です。
あの日から14年を振り返るどころではなく、
大船渡の山林火災で大変な思いをされている方への想像力を働かせる今です。
自分が東京で出会った大船渡出身の友人は、東日本大震災の津波でご実家が被害に遭い、いつか大船渡の力になれることを願い東京で働き、満を持して故郷にUターン。その後ご結婚されお子さんが生まれて今回の山林火災。
高台移転された家から小さなお子さんを連れて避難所に避難しているところで連絡が付きました。
避難解除が出て帰ってみるとご実家は無事だったとのことですが、沿岸部で被災され高台に移転された方の少なからずが大きな被害に遭っていることに、行き場の無い悲しみを感じてしまっているとのこと。
被災の対岸に暮らす自分ですが、あの日から14年経ってもまだまだやれること、やるべきことばかりだなと。
引き続き東北に心寄せてまいります。
アップした絵は2021年にフィールドワークした大船渡の風景。
「高台」と言われる場所にお家が何軒か並び、そこから見えるリアスの海では牡蠣の養殖の筏が並び、ボクの足元ではたくさんのフランスギクの白い花が太平洋からの風に揺れていました。
*その時のことはこちらに記しています> https://www.daihatsu.co.jp/lyu_action/book/no03/madowoakete03/
この美しい場所は被害に遭っていないだろうか?
時を見て、また足を運んでみるつもりでいます。
大船渡のみなさま、まずはご健康であられますよう心よりお祈り申し上げます。

自分は今「東日本_能登の杣径」と名付けた個展を開催中です。
昨年の元旦に発生した能登半島地震と9月の豪雨、その被害の深刻さに触れ、無力感に首まで浸かるも。それ以前に出会った豊かな能登への恋心のようなものにフォーカスし、描いた絵を展示しています。
連日足を運んで下さる方と能登にまつわる会話を重ね、描いた絵を指差し「この場所にはこんな思い出がある」とか、「ここにはこんな花が咲いていた」とか、「ここで会った人と見たものは」などなど、それは拙い経験でしかないのだけど、自分なりの「能登物語」をシェアする展覧会になっています。
言葉で伝えきれぬ能登の魅力を人に伝えられる、もしくは、言葉にしづらかったことを一枚の絵があるからこそ言葉できる、それは結局とてもイラストレーション的なことなんだろうな。
そんな絵1枚1枚をなぜ自分は描いたのか?
風景でも、花の絵でも、人の姿でも、自分の中の何かが共鳴して「描きたい!」と思うわけなんだけど、その「自分の中の何か」とはなんだろう?
何かを見るということは、実はそのほとんどすべては「自分に都合の良いものだけ」を選んで見ていたりするんだろうなと。
私たちは日々「見ているようで見ていない」と「見るとも無く見ている」繰り返して生きているはずで、そんな「見る」が「描きたい!」になる瞬間、自分の中の何と共鳴しているんだろう?
「都合の良いものだけ」を「生きるに足るものだけ」と置き換えると、より自分のやっていることに近づいた表現になるはずだけど、自分の場合は「描きたい!」から行き先を決めず描き始め、描きながら自分の中に埋まっているものと会話し、ある瞬間自分の中の何かと接続した瞬間、絵が完成するって感じです。
じゃあ「自分の中の何か」とはなんだろう?
それは子供の頃の穏やかな記憶だったり、ある時受けた心の痛みだったり、人を傷つけてしまった後悔だったり、息子が生まれてからしばらくの凪のような日々の記憶だったり、、
今なら、東日本大震災の被災地で出会ったことも、たとえば能登の風景をボクに見せてくれるスイッチになっているはず。
ただ、自分が描いた1枚の絵が、実際は自分の中のどんな記憶と接続しているのかは分からず。
なんだけど、でも確かに過去の何かとは接続している実感のある絵は、「分からない」からこそ答えを出すことの無い揺らぎを抱えたまま、自分と絵に向き合って下さる方との間に、優しく誠実な会話が出来る余白を作ってくれ、ボクはお客様と能登について、大船渡について、東日本について、時間が許す限り会話を続けられています。
このことは、自分の命が続く限り止まることはないだろうし、止めるつもりのないのです。
2枚目にアップした絵は、2017年5月に会津で出会った風景。
会津は自分が知る限り日本でも最も美しい光に出会える場所。
それを描くのはとても大変なことで、この風景を自分は何度も描いてきました。
東日本大震災の痛ましい被害の現場を歩き、そのリアルを自分の中に刻み込む作業の隣には、
描くべき美しいものとの出会いもあり、そのポジティブなマインドこそ、息子たち世代に渡してゆきたいものだと考える今です。